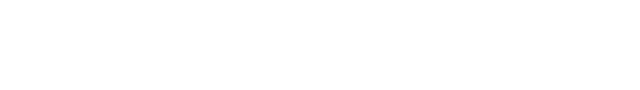社交不安障害
他者との雑談などの社交的なやりとりや、注目を浴びる場面などで、強い不安・恐怖を感じやすい方に見られる疾患です。
具体的な症状と診断
・人前に出ると緊張しすぎて思うように話ができない
・頭の中が真っ白になってどうしたらいいか分からなくなる
・ドキドキする
・声や体が震える
・冷や汗が出る
人前でこれらの症状が現れ、そのような自分の言動・表情で、「他人に変に思われているのではないか」、「軽蔑されるのではないか」と不安になり、時には恐怖を抱くこともあります。
1年間で約2.8%の人々が罹患し,生涯有病率は約5%と報告されています(1)。
症状が出やすい場面は,人前でのスピーチや演奏、会食、初対面の人と会う、などが挙げられます。ごく身近な人や、逆に全く見知らぬ人と同席する時には症状が起こりにくいと言われています。
軽度のものなら多くの人が経験しますが、症状がひどくて本来の生活が送れない場合、たとえば、患者さんがその状況を意図的に回避するため、日常生活が大きく制限されてしまい、送りたいはずの生活を送ることができない場合はこの診断となります。
治療
上記のような傾向があっても本人がそれに気づかないこともあり、社交不安のある人の多くは、自ら治療を求めることが少なく、代わりに下記のような自己流で解決しようとする場合があります。
・社交場面を最小限に減らしたり避けたりする
・飲酒で解消しようとする(解消にはならず、依存など別の問題に繋がる可能性があります)
・ただ我慢をする
しかし上記のような対応では解決につながらない場合が多いようです。また、あまりにも物事を回避してしまい、そのような行動様式が定着してしまうと、回避自体が問題となり、ポジティブな体験をする機会を失ってしまうことがあります。
実際には、複数の治療の選択肢がありますので、早期の治療が望ましいと言えます。
大きくわけて、心理療法と薬物療法です(2)。
心理療法は、不安についての一般的な対処法から取り組んでいきます。
薬物療法は、抗うつ薬に分類されるエスシタロプラムやフルボキサミンなどのSSRI、または抗不安薬を用いて行います。SSRIについては、年齢への配慮が必要となる場合があります。抗不安薬の一部は依存性が問題となる場合がありますので、頓服としての使用や短期的な使用から考慮しますが、継続的な使用となる場合もあります。
まずはお話をうかがい、個々の患者様の状態に応じて、当院で提案できる治療法についてご説明していきます。
参考文献
1.Grant BF, Hasin DS, Blanco C, et al: The epidemiology of social anxiety disorder in the United States: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions.J Clin Psychiatry66(11):1351-1361, 2005 .doi: 10.4088/jcp.v66n1102
2.Williams T, McCaul M, Schwarzer G, et al: Pharmacological treatments for social anxiety disorder in adults: A systematic review and network meta-analysis.Acta Neuropsychiatr 32(4):169-176, 2020.doi: 10.1017/neu.2020.6
現代臨床精神医学(金原出版)